学 生
〜 WELCOME TO IC TEAM 〜
国際協力学研究室のゼミは、International Cooperation and Development Studies の最初の2語の頭文字をとって ICゼミと呼ばれています。大学院生どうし、学部生どうし切磋琢磨することはもとより、院生・学部生がともに学ぶ機会もあります。和気あいあい仲のいいゼミです。

国際協力学研究室(IC ゼミ)のメンバー
(リモートでのゼミ参加者もいます)
(リモートでのゼミ参加者もいます)
大学院生の紹介
ちょっとプロフィール
研究テーマ
鄒 越
- 研. 猫に関すること全般に興味があります。
- 男性の月経観に関する研究-日中両国の 20 代大学生を対象として
門上 綾
- D.開発コンサルタントの社会人学生
- バングラデシュ国における持続可能な給水施設の運営・維持管理及びモニタリング実施促進を行う上での関係機関/者間の体制確立のための阻害要因及び促進要因
マイヤー清水幸子
- D.サヘル地域と仏語圏ギニア湾諸国を専門とし、衛生、水、保健、地域文化に関心
- 国際基準の感染症対策、地域文化、衛生教育の関係性に関する考察
小塩若菜
- D.ファシリテーションが得意です
- ジンバブエにおける都市化と月経対処の変容
宮村侑樹
- D.関西の美味しいお店を巡るのが趣味です
- インドにおける出稼ぎ労働者の子どもの教育
付 若琳
- D.お酒とお花が好きです。
- 中国農村部における女子児童の月経対処と月経観の形成 ―世代間継承と変容の視点から―
山口菜々果
- D."Japo sipati tamaa sikati" この言葉をモットーにしています。
- 学校と地域社会の関係性にみる教育の「公共性」の再考-ケニア農村部の事例から-
松本ミユ
- D.ペンギングッズを買いあさっています。
- 日本における教員の性教育実践を支える要因に関する研究
小松勇輝
- D. 少年老い易く学成り難し。
- 仏語圏西アフリカの生活世界と非認知能力から教育開発における教育の質を問い直す
熊野海音
- M.朝にコーヒーを飲まないと起きた気がしないです
- 身につける生理用品の違いからみられる身体の主体性 ―月経カップに着目してー
チャウ・ファム
- M.ベトナム留学生、ライブ参戦らぶ
- ベトナムの家庭での性教育によるコミュニケーション
長野怜香
- M.国内外問わず旅行が好きです
- 国境のない気候難民の二重脆弱性
ブイ・ヴァン・アイン
- M.ベトナムのハノイの出身です。自然が大好きでハイキングとカメラ散歩が趣味です。
- 自然災害時におけるベトナム沿岸部に住んでいる女性の月経衛生対処
松井響
- M. 猫が好きで、保護猫2匹と暮らしてます。
- 学校現場のトイレにおける感染症予防対策の在り方についての一考察 -大阪府の公立小学校を事例に-
伊藤久美
- M. 看護師、保健師。アフリカ好き。
- モザンビークにおける月経衛生対処(MHM)教育支援の実情と課題:教員と女子児童の語りを手がかりに
範褚卉
- M. 知らない道の素敵なお店が好きです(帰りはほぼ迷子)。
- 災害時における月経衛生対処とその支援 ― 日中比較に着目して ―
松本真衣
- M. プレママ社会人学生です。もともとはビールが大好きです!
- 難民と受け入れ地域住民の共生について ―ウガンダのコンゴ民主共和国難民運営校を事例に―
早川眞央
- M. カフェ巡りが好きで、行きたいカフェをグーグルマップに沢山保存しています。
- ブルンジにおける伝統的な課題解決の場の実践分析


海外でフィールドワーク中の学生と教員
近年の博士論文 題目
| 年度 | 氏名 | 論文タイトル |
| 2023 | 羅 方舟 | アフリカから中国への留学生移動の新たな形態と構造―留学動機、進路選択、帰国意志に着目して― |
| 2021 | Andriamanasina Rojoniaina RASOLONAIVO | Policy and practices of Citizenship Education in Madagascar: Situating the perceptions of local stakeholders within the global discourse |
| 2021 | Fanantenana Rianasoa ANDRIARINIAINA | School education and family involvement in children's preparedness for school to work transition in rural Madagascar |
| 2018 | 金子 聖子 | マレーシアにおける留学生の教育から職業・移民への移行 ―国境を越える高等教育の役割の再検討― |
| 2018 | 小川 未空 | ケニア農村部の中等教育拡充期における格差と公正 |
| 2016 | 小笠原 理恵 | 日本の医療における文化的および言語的マイノリティ住民 |
| 2016 | 山本 香 | シリア難民がつくる学校教育の役割 ―避難国トルコにおける連帯と分断― |
| 2015 | 日下部 光 | マラウイの遺児の生活と学校教育 ―中等教育の就学継続に着目して― |
近年の修士論文 題目
| 2024 | 付若琳 | 中国農村部の寄宿学校における女子児童の月経対処の実態と背景要因 -貴州省の公立小学校でのフィールド調査をもとに- |
| 2024 | 山口菜々果 | ケニアにおける保護者と学校教員の「教育熱」-農村部および都市スラムにおけるフィールドワークを通して- |
| 2024 | 早川 穂乃花 | フィリピンのスラムにおける子どもの生活環境が教育に及ぼす影響 -元廃棄物処分場周辺コミュニティにおけるフィールド調査をもとに- |
| 2024 | 小島理紗子 | 日本の女子刑務所における受刑者間の月経対処の格差-個人のもつソーシャルサポートに着目して- |
| 2023 | 小松勇輝 | コートジボワールにおける初等教育の質と非認知能力の涵養プロセス ―学校教育と徒弟制で形成される自己効力感に着目して― |
| 2023 | 三浦遥 | ネパールの男性教員による月経教育の意義と課題 -カトマンズ市における男性教員当事者へのインタビューから- |
| 2022 | 小塩若菜 | 高校生の月経対処からみる日本の月経教育の課題 ―大阪の教師と生徒の語りから― |
| 2022 | 長野優希 | ケニアのキベラスラムにおける無資格教員と低学費私立学校の関係 ―教員の生活戦略に着目して― |
| 2022 | 畠山尚之 | 大阪・関西ユネスコスクールネットワークの活動が参加者に及ぼす影響 ―持続可能な開発のための教育(ESD)をテーマとした学び合いに対する質的研究― |
| 2022 | 宮村侑樹 | インドにおける国内出稼ぎ労働者の子どもへの期待と教育選択 ―家族で出稼ぎをする保護者の視点に着目して― |
| 2022 | 山田恵里花 | ルワンダのポストジェノサイド世代が学んだ平和構築 ―日常生活から実践する非暴力と和解― |
| 2021 | 曽莉茹 | 中国政府との関係が国際NGOの活動にもたらす影響 ―雲南省における国際NGOとOxfam Hong Kongを例として― |
| 2021 | 太田朱里 | ケニアの初等学校社会科教科書にみるジェンダー観 |
| 2021 | 余 星瑶 | The social network building of African business migrants in Guangzhou, China: From the perspective of South-South migration |
| 2021 | ツウィ テンソク | 中国貧困地域の教育に携わる学生ボランティアの成長と変容
―南京大学「研究生支教団」を事例として― |
| 2020 | 友田昭二 | Preventing non-infectious diseases due to obesity and elongated life-spans in developing countries |
| 2020 | 森本莉永 | 住民参加型の農村開発における援助アプローチの検討 ―PRRIEアプローチを事例として― |
| 2020 | 羅 方舟 | 中国におけるアフリカ人学生の留学動機と留学経験に関する考察 ―アモイ大学の学位取得型留学生を事例に― |
| 2020 | 李 萍 | 中国農村部における留守児童の生活実態と修学軌跡 ―留守経験がある大学生のライフコースに着目して― |
| 2018 | 久保田 麻友 | マレーシアに滞留するロヒンギャ難民の生活と教育 ―クアラルンプール近郊における学習センターの役割に着目して― |
| 2018 | Andriariniaina Fanantenana Rianasoa | Exploring the trajectory of the children from school to work in the rural area of Madagascar: Insight into the villagers' livelihoods |
| 2017 | 清水 彩花 | 南スーダン難民の就学に対する難民対策の影響 ―ケニアおよびウガンダの初等・中等教育の事例から― |
| 2017 | 田中 裕子 | 医療通訳者の配置が保健医療機関に与えた影響 ―三重県内の病院と保健センターに対する調査より― |
| 2017 | 李 霽 | ケニアにおける孔子学院の運営と教育協力としての役割 ―中国人ボランティア教師とケニア人学生に着目して― |
近年の卒業論文 題目
| 2024 | カンボジア農村地域におけるポイ捨て行動の実態と要因 |
| 2024 | スリランカのジェンダー問題に対するフェアトレードの作用 |
| 2024 | ラオスにおける障害者スポーツ支援事業の自立した運営に向けた課題 |
| 2024 | 地方出身の女子大学生が大学進学を決定した過程 |
| 2024 | フィリピン・セブ市に暮らすバジャウと周辺住民との共生 |
| 2024 | ロマの人々の支援に関わる活動家のライフストーリー |
| 2024 | ケニア農村部の地域社会におけるアグロフォレストリーの役割 |
| 2024 | 児童養護施設出身者の進路選択における影響要因 |
| 2023 | 男性フェミニストによる日本のジェンダー平等に向けた実践 ―男性学・男性性研究の視点と当事者の語りから― |
| 2023 | 在日クルド人の子どもの生きづらさ -学校教育をめぐる課題に着目して- |
| 2022 | 日本における移民による起業の課題 ―起業家と支援機関へのインタビュー調査を踏まえて― |
| 2022 | ビルマ出身移民の子どもが通う学習センター教員のライフストーリー ―タイ・メーソート郡の移民学習センターを事例に― |
| 2022 | オーストラリアにおける音楽教育を通じた多文化理解 ―ニューサウスウェールズ州の中等教育学校で行った調査を基に― |
| 2022 | ガーナのクランが地域社会に与える影響と所属者のアイデンティティ ―アクラの非正規市街地におけるアベセクランを事例として― |
| 2022 | ガーナの非正規市街地におけるコミュニティと小学校の関係性
―クランコミュニティと教員の視点から見た課題と可能性― |
| 2021 | 国際ボランティア活動におけるICT活用の可能性 ―COVID-19感染拡大下でのNPO法人NICEのオンラインプロジェクトを事例に― |
| 2021 | COVID-19感染拡大下の留学における渡日の意義 ―日本語学習のオンライン化の可能性と課題をもとに― |
| 2020 | プラスチック削減方法としてのプラスチックフリー店の課題と可能性 ―イギリス・リーズ市におけるプラスチックフリー店を一例として― |
| 2020 | 元子ども兵の受け入れ家族・コミュニティによる受容の要因 ―ウガンダ北部における社会復帰を事例に― |
| 2020 | インドネシアの公共水道普及における住民の飲料水水源選択からみた課題 ―ジョグジャカルタ特別州を事例に― |
| 2020 | 日本国内における異文化理解教育へのメディアアートの利用可能性 |
| 2020 | グアテマラ内戦後の社会における内戦の記憶の継承 ―社会的記憶の形成が招く社会の分断に注目して― |
| 2020 | サブサハラ・アフリカ地域におけるモバイルマネーを通した金融包摂 ―個人属性に着目した利用普及背景の分析― |
| 2019 | トルコ都市部における地域住民が行う難民支援活動の意義 ―共生に向けた取り組みに着目して― |
| 2019 | タンザニアにおけるティンガティンガ・アートの多様化 ―アーティストから見た真正性に着目して― |
| 2019 | ブラジルの学校給食制度における家族農業の活用の課題と可能性 ―子どもと地域社会にもたらす影響に焦点を当てて― |
| 2018 | ザンビア都市部を生き抜く若者の収入実践 ―ルサカ・ンゴンベコンパウンドを事例に― |
| 2018 | フィリピンの環境教育に見る生きる力を育む要素
―ネグロス島でのインタビューを通じて― |
| 2018 | 社会問題に取り組んだ学生のキャリア選択 ―サードセクターの人材活用をめぐる課題をもとに― |
| 2017 | 酒蔵ツーリズムを通した地域振興 ―伏見区大手筋商店街の取り組み― |
| 2017 | 日本社会におけるボランティア活動に対する視線 ―学校教育におけるボランティア学習を通しての一考察― |


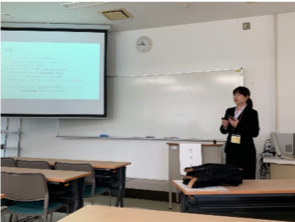
院生も学部生も積極的に学会発表をおこなっています
